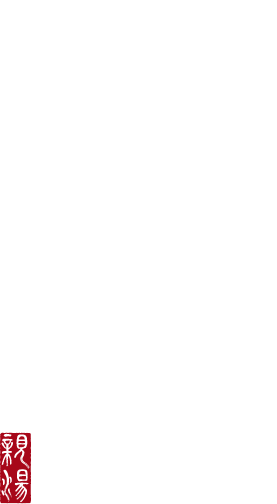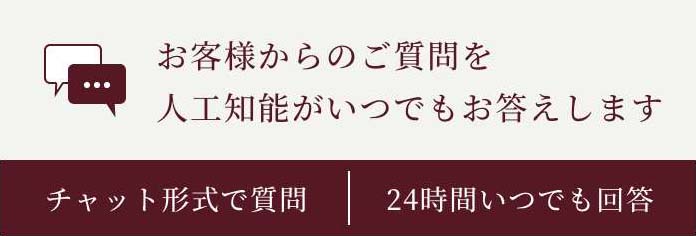今も残る赤彦の足跡
アララギ派の歌人、島木赤彦は諏訪に生まれ、40歳近くまで長野県に暮らしました。そのため、長野県内にはたくさんの赤彦の足跡が点在。歌人として活躍しながら、教育者として心血を注いだ赤彦ゆかりの地を紹介します。

◆島木赤彦誕生地跡碑 諏訪市元町
明治9年(1876年)、赤彦は旧上諏訪村角間に塚原浅茅とさいの四男として生まれました。生家はすでにありませんが公園になっており、良寛さまを歌った童謡碑が立っています。
「山を下った良寛様は
村の子どもと毬ついてゐたが
山に帰った良寛さまは
寺に一人で寂しかろ」
◆玉川小学校 茅野市玉川
赤彦は15歳、24歳、そして35歳と三度にわたって茅野市の玉川小学校に赴任しています。24歳のとき、庭に合歓の木があったことから宿直室を禰牟庵(ねむあん)と名付け、短歌や俳句などの勉強会を開催。近隣からも文学の好きな青年らが集まったといわれます。現在、玉川小学校は移転しているため、玉川神の原農協のスーパー「サンライフ」の敷地に「禰牟庵跡碑」が立てられています。また、玉川小学校の敷地内にも歌碑があり、赤彦自筆の職員会議録や愛用した土瓶なども保存されています。

◆柿蔭山房(しいんさんぼう) 下諏訪町北髙木
赤彦が結婚して養嗣子になった久保田家の旧家。以後、大正15年(1926年)に亡くなるまで、歌人として、また教育者としての幅広い活動の拠点になりました。周辺は柿の木が多く、赤彦は柿の実の赤い色が好きだったことから、「柿蔭山房」と命名したといわれます。母屋には、赤彦の書斎のほか、養父母の居間、子供部屋などがありました。諏訪湖や家族の歌を400首以上、そしてほとんどの童謡がこの家で作られたと言われます。
茅葺の母屋は江戸時代の文化文政頃(1804年~1829年)に建てられたと考えられ、問口が七間半(13.5m)、奥行さが六間(10.8m)。土蔵のほか、庭には樹齢二百数十年といわれる老松が植えられ、赤彦の家というだけでなく、士族の家としても貴重なものです。
※庭園はいつでも見学可能。内部見学については下諏訪町立諏訪湖博物館・赤彦記念館に事前の申請が必要です。
◆下諏訪町立諏訪湖博物館・赤彦記念館 下諏訪町10616-111
諏訪湖畔にある博物館。諏訪湖展示室では、「諏訪湖と人々のくらし」をテーマに諏訪湖の成り立ちや生態系、漁具、スケート、氷切り、御神渡りなどを紹介。 赤彦展示室では、赤彦の書や書籍、帽子・硯・鉛筆といった愛用品など、アララギ派の活動関連資料を展示しています。

上記のゆかりの地以外にも赤彦の碑は長野県内の富士見町や塩尻市などに25ほど点在しています。また、姉妹館の蓼科 親湯温泉ではアララギ派の歌会も開催され、実際に赤彦も訪れたことから、赤彦をイメージしたお部屋(蓼科倶楽部の内1室)もあり、今でもファンが多く訪れます。ぜひ、アララギ派の中心人物として活躍した赤彦のゆかりの地を訪ね、当時の文学の世界をたっぷりとお楽しみください。