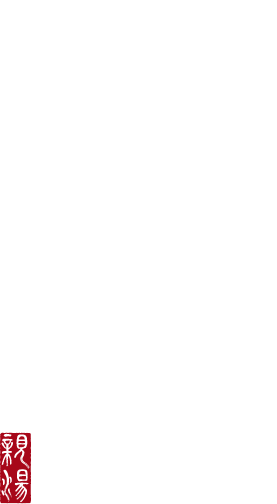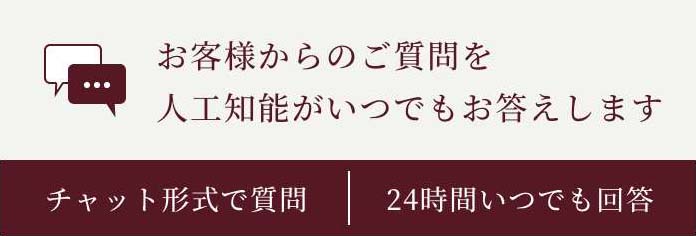上社独自の4つの不思議




諏訪大社は日本最古の神社の一つとして、また全国に約25,000社ある諏訪大社の総本社として広く知られています。諏訪湖周辺に上社と下社があり、上社には本宮・前宮、下社には秋宮・春宮、二社四宮が鎮座。それぞれの社殿の四隅には御柱が建てられ、社殿の配置も独特の形をしています。また6年に一度(7年目に一度)開催される御柱祭も有名です。

そんな諏訪大社には古くから伝わる七不思議があります。これは、諏訪大社の行事や神事に関わる不思議な現象のこと。怪談ではなく、あくまでも諏訪大社の行事や神事に関わる不思議な現象のことをいいます。
七不思議といっても、上社に4つ、下社に4つ、共通の不思議として3つがあり、上社下社それぞれに7つの不思議、トータルでは11の不思議が存在しています。今回は、上社独自の4つの七不思議を紹介します。

元朝の蛙狩り(がんちょうのかわずがり)
元日の朝に本宮で行われる蛙狩神事(かわずがりしんじ)のこと。御手洗川の神橋の上、一段高い所で、氷を割って川底を掘り返すと、厳冬にも関わらず必ず2匹蛙が捕獲できるのだそう。捕まえた蛙は生贄として神殿に捧げ、国家平安と五穀豊穣を祈願します。
高野の耳裂鹿(こうやのみみさけじか)
毎年4月15日に開催される上社最大の神事、御頭祭(おんとうさい)にちなんだ不思議です。現在は鹿や猪のはく製が使用されていますが、かつての御頭祭では上社前宮の十間廊に鹿の頭が七十五頭、兎の串刺しや猪などが供えられ、禽獣(きんじゅう)の高盛と呼ばれていました。当時は、神前に捧げられた鹿の頭の中に、毎年必ず1頭は耳の裂けた鹿がいたと伝えられています。
葛井の清池(くずいのせいち)
諏訪大社上社の摂社の1つ葛井神社(茅野市)に伝わる不思議。上社の年中行事の最後となる「葛井の御手幣(みてぐら)送り」の神事の際、上社本宮の御幣殿にお祀りしてあった御幣束を葛井神社の池に沈めると、元日になると遠州の佐奈岐池にその御幣が浮かび上がるといわれています。また、この池は底なしで、池の主として片目の魚がいるとも伝えられています。
宝殿の点滴(ほうでんのてんてき)
どんなに干天が続いても、上社本宮の宝殿の屋根からは最低三滴の水滴が落ちてくるといわれています。日照りの際には、この水滴で雨乞いをすると必ず雨が降ったともいわれ、諏訪大社は水神としても知られています。
さまざまな不思議が残る諏訪大社。諏訪大社を訪れた際は、七不思議にまつわる場所を訪れてみると、また違った楽しみ方ができるのではないでしょうか。