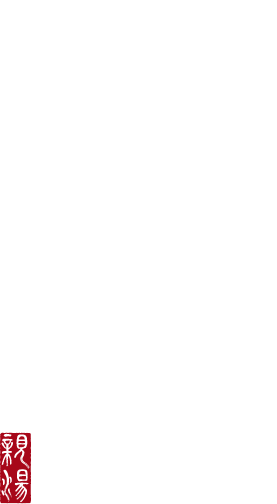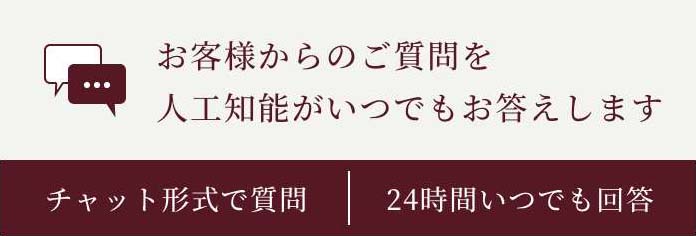知る人ぞ知る寒鰻のおいしさ
タンパク質やビタミン、ミネラルなどを豊富に含み、栄養満点のうなぎ。うなぎは蒲焼きで食べられることが多いですが、蒲焼きというスタイルが始まったのは、なんと室町時代からです。当時は、うなぎを丸ごと串に刺して焼いていました。この様子がガマという植物の穂に似ていることから、「がま焼き」→「蒲焼き」と変化したといわれています。
うなぎを開いてから串に刺して焼く、現在のスタイルになったのは1700年ごろです。けれども味付けには味噌や酢を使用。醤油を使用した蒲焼きもありましたが、身に味が染み込まず、試行錯誤が繰り返されました。1700年代から1800年代にかけては国産砂糖が広がるほか、みりん・酒などの甘み調味料の普及し、またうなぎをさばく技術も進歩していきました。関西では、醤油と酒で作ったタレをつける手法が開発され、少しずつ広まっていったともいわれます。
現在のスタイルである江戸前の蒲焼きが誕生するのは、江戸時代中期になってからです。当時はまだ江戸前寿司がなかったので、「江戸前」といえばうなぎの蒲焼きのことをさし、屋台で売られていました。
けれども、当時夏場はうなぎの売れ行きがよくありませんでした。その理由は、うなぎの旬は夏ではなかったからです。また、蒲焼きのこってりとした味は夏向きではなかったことも大きな原因でした。そこで、平賀源内の案によって登場したのが「土用丑の日」の看板です。「精のつくうなぎは夏を乗り切るのに最適」という宣伝文句で売り出したところ、うなぎは飛ぶように売れ、今でも「土用丑の日」にはうなぎを食べる風習が根付きました。
では、うなぎが一番おいしい時期はいつなのでしょうか。うなぎの旬は秋から冬にかけてです。このころのうなぎは産卵前で、脂をたっぷりと蓄え、絶品です。そもそも「土用」とは、立春・立夏・立秋・立冬の前十八日間のことをいい、年に4回あります。「丑の日」はその期間中に1度ないし2度巡ってきます。そこで岡谷市では、うなぎが旬を迎える時期に合わせて、立春前の土用を「寒の土用丑の日」と制定しました。これは日本記念日協会にも登録され、「寒の土用丑の日」発祥の地として、最もおいしい寒のうなぎを全国に広めています。
上諏訪温泉 しんゆでは、スイートルームへご宿泊のお客様にはうなぎの釜飯をご用意しております。ぜひ、うなぎの名産地である諏訪地方で、長い歴史が育んできた味をお楽しみください。