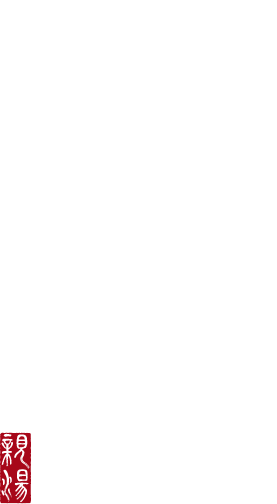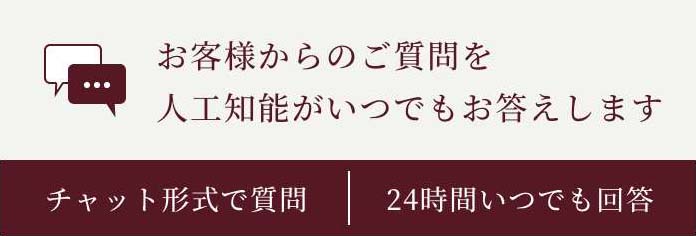伝統の味わいの秘密

タンパク質やビタミン、ミネラルなどを豊富に含み、精がつくといわれるうなぎ。うなぎといえば、静岡をはじめ鹿児島や愛知、宮崎などが有名ですが、諏訪湖周辺にはうなぎの専門店が数多く点在し、激戦区として知られています。
江戸時代から、諏訪地方に暮らす庶民たちはうなぎを味わっていたといわれます。静岡県浜松市から天竜川を上り諏訪湖で育ったうなぎは、昭和初期には約38トンもの漁獲量があり、湖畔には多くのうなぎ専門店が点在していました。中でも「うなぎのまち」としても知られる岡谷市は消費量もトップクラスで、今でも冠婚葬祭だけでなく保育園・小学校・中学校の給食にもうなぎが出るというほどです。
うなぎは蒲焼きで食べられることが多いですが、関東風と関西風があります。関東風は、さばきは背開きで、うなぎを蒸してから焼きます。武士文化が根付いていた江戸では「腹開き=切腹」を意味することから背開きになったといわれます。関西風は、腹開きで、蒸さずに焼きます。商人の町として知られる大阪では「互いに腹を割って話そう」という思いから、腹開きになったといわれます。

ここでおもしろいのが関東と関西の中間地点にあたる諏訪地方のうなぎです。諏訪地方のうなぎはお店によってさまざまですが、岡谷市のうなぎ店では、さばきは関東風の背開き、焼きは関西風で蒸さないというのが特徴です。代表的な焼き方は、背開きにしたうなぎに金串を打ち、皮側からじっくりと炭火で焼き、表面に火が通ったら裏返し、何度もそれを繰り返してこんがりとキツネ色に焼き上げます。濃く甘いタレは最初は軽く、味が染み込んできたらじっくりとタレに漬け込んで、こげないように注意しながら、タレに付けては焼くという工程を何度も繰り返します。仕上げには、たれをしっかりと染み込ませ、軽く焦げ目がついたら完成します。
焼きあがったうなぎは、皮はパリパリ、身はふっくらで、素材の旨味がぎゅっと詰まった至極の味わい。食べた瞬間に、香ばしさと濃厚な味わいが口いっぱいに広がります。また、それぞれの店がしのぎを削る激戦地というだけあって、店ごとに秘伝のタレを使用し、趣向を凝らしたメニューを提供してくれるのもこの地域ならではです。
暑い日が続く今年の夏。少し気温が低く過ごしやすい諏訪湖へ、栄養満点のうなぎを食べに訪れてみませんか?
→次号も、諏訪湖畔のうなぎについてご紹介します。