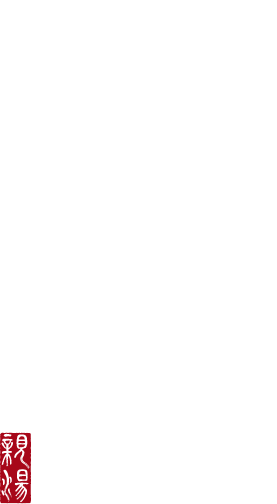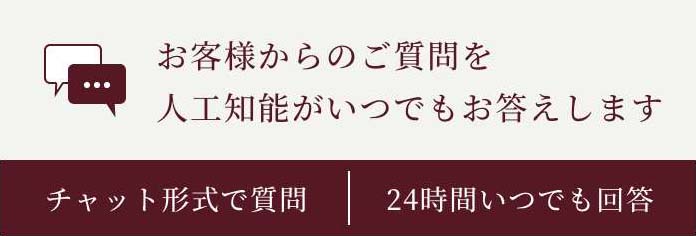戦国時代から明治維新までの歴史

天文8年(1540年)、「諏訪氏中興の祖」といわれる諏訪頼満が病死。嫡男の頼隆が若くして急死していたため、孫である頼重が家督を継いでいましたが、天文11年(1542年)には、武田晴信(信玄)の信濃侵攻によって頼重が自刃。諏訪惣領家は一時的に滅亡しました。このとき、高遠城を居城としていた諏訪氏一門の高遠頼継は、晴信と内通して諏訪攻略を援護していたことから、諏訪領は武田氏と頼継が分割。けれども諏訪氏惣領を志向する頼継はそれを不服とし武田領へ侵攻しました。宮川の戦いで敗退した頼継は、諏訪から撤退。その後、高遠城は落城し、頼継も自害して、高遠氏も断絶したといわれていました。また、近年の研究によると、永禄5年(1562年)に諏訪惣領家を継いだとされていた信玄の四男の勝頼が高遠諏訪家を継いでいたという説もあります。

天正10年(1582年)、織田・徳川同名の信濃攻めで武田氏が滅亡し、その後領地を掌握した織田信長が本能寺の変で自害すると、織田氏の領国支配体制が固まっていなかった旧武田領国(甲斐・信濃・上野西部)は混乱。この旧武田領国をめぐって、後北条氏(北条氏政・北条氏直)、徳川家康、上杉景勝が争い、そこに武田氏の傘下だった木曽氏や真田氏、旧信濃守護の小笠原氏などが絡み、天正壬午の乱がおこります。その中で、頼重の従兄弟である頼忠が諏訪氏を再興し、諏訪領の支配を回復。さらに、信濃国の大半を支配した徳川家康の配下に入り、天正18年(1590年)の家康の移封に伴って、頼忠も武蔵国1万2000石へ、2年後には上野国へと移りました。

関ケ原の戦いでは、頼忠の息子である頼水が徳川秀忠軍に従って信濃国や上野国を守り、第二次上田合戦後には上田城の受取役を果たすなど、徳川方で戦功をあげました。その結果、慶長6年(1601年)、諏訪家はようやく旧領の信濃国高島藩(諏訪藩)2万7,000石へと復帰。さらに慶長19年(1614年)からの大坂の陣では、甲府城を守り、頼水の長男である忠頼が出兵しました。この功績により5000石を加増。明暦3年(1657年)には、一族に2000石を分与したことで3万石になりました。

その後、高島藩(諏訪藩)は、明治4年(1871年)に廃藩置県が行われるまで、3万石のまま諏訪の地を治め、明治維新後は子爵となりました。