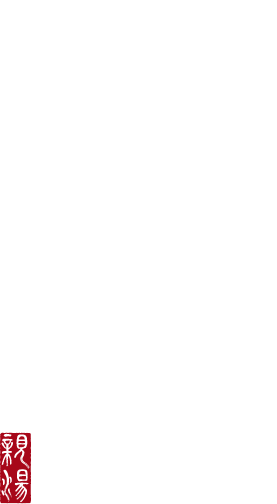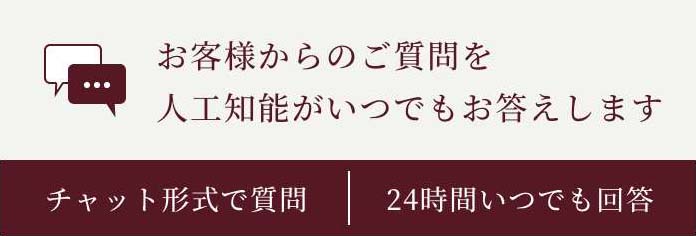その成り立ちと歴史

中・近世の時代、諏訪地方を治めていた諏訪氏。諏訪氏の名前は戦国時代を舞台にした小説『風林火山』『武田信玄』などでご存じの方も多いのではないでしょうか。今回は諏訪氏の出自や歴史についてご紹介します。

諏訪氏の出自については、建御名方(たけみなかた)神の子孫、桓武天皇(かんむてんのう)の子孫、清和源氏(せいわげんじ)の末など諸説あります。最も一般的な説は、信濃(科野)国造を賜ったという武五百建命の後裔(こうえい) 金刺舎人(なかさしのとねり) 直金弓の子孫とされ、金弓の孫となる乙頴は諏訪大神(現在の諏訪大社)上社の大祝(おおほうり)になったといわれます。また、乙頴の兄である倉足は科野評督になり、その子孫が貞継のとき下社の大祝になりました。

平安時代末期になると、諏訪上社の大祝が諏訪氏と称し、神官であると同時に武士としても活躍。諏訪地方の武士団の長として各地での戦役に派兵するようになりました。前九年(1051年)・後三年(1083年)の役では、大祝為信の子である為仲(諏訪為仲)が源氏軍に参加。さらに保元の乱では平吾が源義朝の軍に加わって戦いました。

鎌倉時代、源頼朝に仕えた盛重は諏訪太郎と称し,幕府の御家人に。その後は幕府の実権を握った北条得宗家の直属家臣となって、北条家所領の管理などを担当し、その後も北条家家政役人の筆頭(内管領)として活躍したといわれます。中先代の乱(1335年)では頼重が一族をあげて挙兵。北条時行を奉じて一時は鎌倉を占領するものの、結局足利尊氏に敗れ、のちに宗良親王を奉じて南朝にくみしました。

室町時代に、北朝が支配的になると、諏訪大社のうち下社の金刺氏が北朝派に転じて上社の諏訪氏と対抗。以後戦国時代まで諏訪郡で領地争いをすることになりました。応仁の乱後、上社大祝諏訪頼満が、下社大祝金刺昌春を攻め落として全諏訪を支配。このことから諏訪氏中興の主といわれています。

戦国時代には、甲斐国の武田氏と敵味方になりながら、生き残りを図っていきましたが、1542年、武田晴信(信玄)によって諏訪頼重が自刃し、諏訪氏の惣領家は一時的に滅亡。その後、頼重の娘は信玄の側室となり、勝頼を産みました。
軍神の扱いを受けていた諏訪大社から武士へと成長していった諏訪氏。一度は滅亡したものの、諏訪氏の歴史はまだまだ続きます。