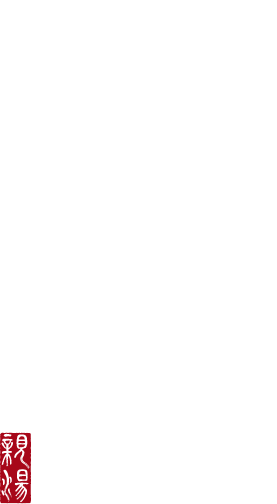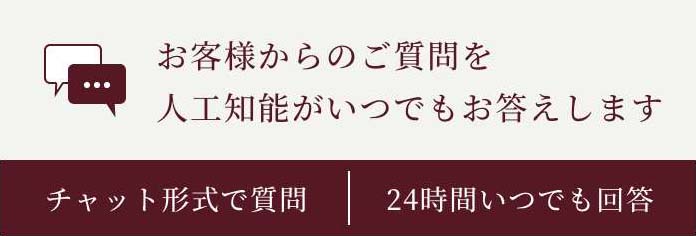当時の面影を感じられる産業遺産群

明治、大正、昭和初期に、日本は製糸輸出量が世界一になりました。その中心となって養蚕業を牽引してきたのは長野県岡谷市だったことは意外にも知られていません。日本の近代化を支えた「Silk Okaya」。今回は現在も当時の面影を残す近代化産業遺産を紹介します。

鶴峯公園
片倉組の初代片倉兼太郎は、明治11年(1878年)に垣外製糸場を創業し、翌年には製糸結社の開明社を設立。明治28年(1895年)には片倉組を創設して、日本を世界一の製糸王国へと導きました。そして、低年齢従業員への教育のために私立片倉尋常小学校を建設。工場法や学校制度の改正などにより学校はなくなりますが、跡地は公園として開放され、今では中部地方有数のツツジの名所に。毎年5月初旬から中旬にかけて30種類3万株のツツジが色づき多くの人が訪れます。公園内には、初代片倉兼太郎の銅像が建っています。※常時見学可能


旧片倉組事務所
明治43年(1910年)に建築された片倉組の本部事務所です。木造2階建て瓦葺き(現在は銅板葺き)、間口13.6m、奥行き24.5m。一階には洋風玄関、二階には和風の大広間があります。平成8年に国の登録有形文化財に認定されました。戦後印刷部局が独立して中央印刷株式会社となって引き継がれ、今もなお事務所として使用されています。※外観のみ見学可能
旧林家住宅
岡谷三大製糸家の一人といわれた初代林国蔵の住宅。初代林国蔵は、豊かな発想と先見性に富み東京の日本橋にビルを構えるほどに成功しました。住宅は主屋と離れの座敷、茶室、洋館に分かれ、主屋の南側には繭倉庫の形式をとどめる土蔵が並んでいます。中でも離れにある二階の和室は西洋装飾の芸術「幻の金唐革紙」と呼ばれる壁紙が天井・壁・襖・床の間の壁全てに張り巡らされ圧巻。国重要文化財にも指定されています。※見学可能
丸山タンク
大正3年(1914年)に、製糸用水の供給のために「丸山製糸水道組合」が結成されました。そして天竜川にポンプを設置して、湖岸から650m離れ、湖面より20m高い丸山に貯水する大規模な揚水施設を設置。塚間川以西の製糸地帯へ潤沢な水の供給が可能になりました。現在はタンクの基台であった直径12mの巨大な三重円筒型レンガ積が残っています。

旧山一林組製糸事務所・守衛所 大正10年(1921年)に建築された旧山一林組製糸株式会社の事務所棟と守衛所建物。山一林組は、明治12年(1879年)に創業し、岡谷でも5指に入るほどの大製糸工場に成長しました。事務所は木造2階建て、外観は洋風ですが屋根は和瓦。一見すると鉄筋コンクリート造りにも見える、製糸業の全盛期を今に伝える数少ない建築スタイルで、国登録有形文化財です。現在は、きぬのふるさと岡谷絹工房が絹織物の制作を行っています。※体験可。要予約