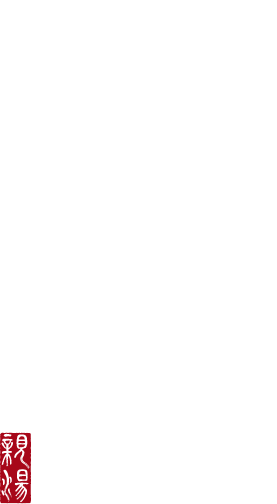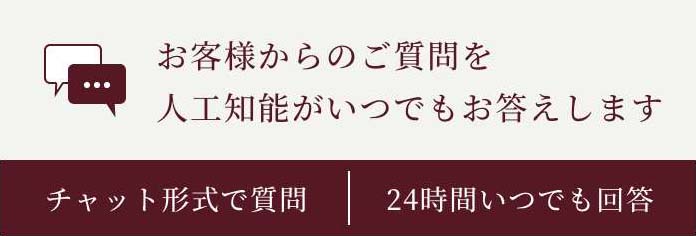岡谷で製糸業が発展した理由

明治42年(1909年)、日本は中国を抜いて世界一の輸出生糸生産国になりました。そしてその時に生産量がトップになったのは、富岡製糸場がある群馬県ではなく長野県だったことはあまり知られていません。さらにその中でも諏訪湖畔に位置する岡谷は長野県の生産量の60%を占め、日本の近代産業の発展に大きく貢献しました。では、なぜ、岡谷でこんなに製糸業が発展したのでしょうか。

諏訪湖畔に位置する諏訪地方は、八ヶ岳を望む風光明媚な土地です。けれども、標高が高いため冬は長く厳しく、一年のうちの11月から3月までの5か月は農耕作業をすることができず、人々の生活はとても苦しかったといいます。そして江戸時代中期以降には、農閑余業として養蚕をはじめ綿打、手紡糸などが行われるようになりました。

岡谷の発展に大きな影響を与えたのは、前回も歴史で紹介したように、「諏訪式繰糸機」を開発した武居代次郎や、世界一の製糸工場まで成長させた片倉一族(片倉財閥)などが挙げられます。これは諏訪地方の人たちには進取の気風があり、質素、倹約、勤勉、忍耐、克己であったからだとも言われます。

また、銀行家である黒澤鷹次郎は、製糸業者への積極的な融資を行い、横浜への生糸輸送にかかる販売代金立替払い(荷為替取組)などを実施。繭倉庫として明治42年に諏訪倉庫を設立し、岡谷の製糸業の発展にも大きく貢献しました。

さらに、工場で働いた女性たちの貢献も製糸業発展の大きな力となりました。明治期は生産効率優先でしたが、大正時代になると労働時間も短くなり、女性たちの教育にも力を入れ国語算数のほか、そろばんや裁縫なども教えていたといいます。女性たちが故郷に帰るときはお土産を持たせるなど、映画『女工哀史』とは異なり、とても大切にされていたことが分かります。

岡谷の発展には環境の影響も大きかったといわれます。岡谷は湿度が低く、繭の乾燥や繰糸後の生糸の乾燥に適していました。また、諏訪湖へ入る川、天竜川などが近くにあり、水力を使用できただけでなく、豊富な水を煮繭・繰糸用水として活用。軟水の性質が製糸に適していました。

各地から鉄砲籠で運ばれた繭をそれぞれの工場へと運ぶ鉄道が整備されたこと、それまでになかった一代交配蚕種の普及、燃料である薪や亜炭などが得られたことなど、さまざまな要因が重なり、岡谷は「糸都岡谷」へと発展しました。そして昭和になると、製糸業の発展とともに、製糸機械メーカー、機械に取り付けるバルブ産業や計器産業も発展していきました。こうした実績があったからこそ戦時中には多くの工場が疎開し、製糸業が衰退した後も、業務転換がスムーズに行われ、東洋のスイスと呼ばれる精密工業都市へと発展したのではないでしょうか。